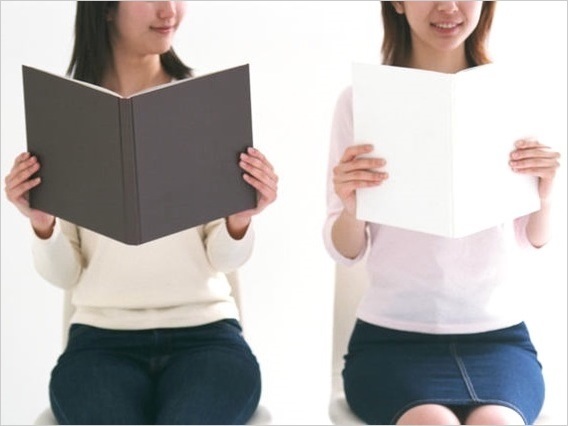皆様のお陰で70年 感謝をこめて授業しています。小学生、中学生、高校生、社会人大歓迎!算数・数学を大好きになりたい方に優しく教えています。詳しくはお電話・メールでお問合せ下さい!
新着情報!
2月27日
ポッドキャスト (音声配信) 第1244回を公開しました
こんな塾があったらいいな
というテーマでお送りします。
あなたが東京大学に進学したいとする。
試験科目は、数学、英語、物理、化学、古文、漢文、現代文、それに共通テストの
社会1科目、情報Ⅰ。
これだけの科目に高水準の学力を持って臨まなくてはならない。
英語一科目でも要約、聴く、読む、書くという能力が試される。
この事実を前にした受験生に私ができることは、
1. 何をやるか
2. それをどうやってやるか
この二つを特定し、受験生に示すこと。
つまり、この道を歩めば絶対に合格する、その道を示すこと。
必要な勉強量は無限ではない。特定できる。
正しい勉強の手順、正しい取り組み方がある。
それらをあなたに何としても、知って欲しいと心から思う。
そして、合格を切に願う。
そして、そして、
この道を私と一緒に歩むことで、
自分のなかにある無限の力に気づいてくれることを確信している。
思う存分その力を発揮してほしい。
最高の高みまで昇って行ってほしい。
絶対合格!!!!!!
再生時間4分半です。ぜひ聴いてみて下さい。
2月20日
ポッドキャスト (音声配信) 第1243回を公開しました
カード学習法
というテーマでお送りします。
カードを作成して、それをいつも持ち歩いて、何度も見直すという
勉強法はとても効果が高い。
効果が高いどころか、カード作成+見直すことで
本当に正しい勉強法を身に着けられる。
さらにすごいのは、生徒の知的好奇心を刺激して、
学ぶことの面白さを生徒自身が存分に味わうことができる。
結果、生徒の創造力を開発することができる。
万能の勉強法なのだが、
それを生徒に実践させ続けるにはコツがある。
絶対合格!
再生時間9分です。ぜひ聴いてみて下さい。
2月13日
ポッドキャスト (音声配信) 第1242回を公開しました
偏差値表を捨てましょう
というテーマでお送りします。
偏差値表を捨てましょう。
他人の噂話も聞かないようにしよう。
そして、一次情報だけを見ましょう。
一次情報とは、卒業生の進路と過去問です。
一次情報を精査するだけで、受験に正しく向き合う道筋が見えてきます。
正しい道筋を確実に歩んでいけば、合格が向こうからやってきてくれます。
絶対合格!
再生時間7分です。ぜひ聴いてみて下さい。
8月 1日
#頼りになる本 のページを公開しました
[お知らせ] 音声ブログ配信日変更について
いつもブログ・音声のご視聴をありがとうございます。
現在週2回の配信を、今週より 毎週金曜日午後3時配信 とさせていただきます。
真の教育を目指して、さらに濃く、深い内容をお届け致します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お子様の入退室をリアルタイムでお知らせするシステムを導入します
お子様の塾の入退室をメールでお知らせします。
詳しくは「安心でんしょばと」のページをご覧下さい
鴨下算数数学塾へようこそ
一人でも多くの方に、
算数・数学を大好きになってほしい。
算数・数学をできるようになって欲しい。
私の思いはそれだけです。
成績を上げたい。どうしても希望の学校に合格したい。
私の喜びは、そういう生徒・児童の皆さんの手助けをすることです。
その生徒・児童の皆さんが、
「先生、数学大好き!」 と目を輝かせて言ってくれたら……。
今日も塾を開いています。
まずお話したい3つのこと
個別入塾説明会を開催しています

鴨下算数数学塾では、随時、個別入塾説明会を開催しております。
何をおいてもまず最初にしなくてはならないことは、お子様の現状を正確に知ることです。
その上で、ご両親様やお子様のお話を伺い、「何をしたらいいか」進むべき最良最善の道を一緒に考えて参りましょう。
お気軽にご連絡下さい。
入塾を希望される方へ
入塾説明会の日程
毎週日曜に随時開催しております。
電話又はメールにてご連絡ください。
お問合せはこちら
音声ブログ
大好きが天才を生む
ポッドキャスト(音声配信)「大好きが天才を生む」 は、
毎週金曜日の午後3時に更新します。